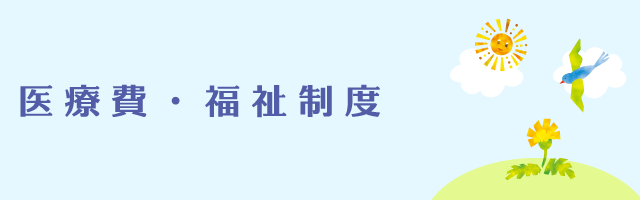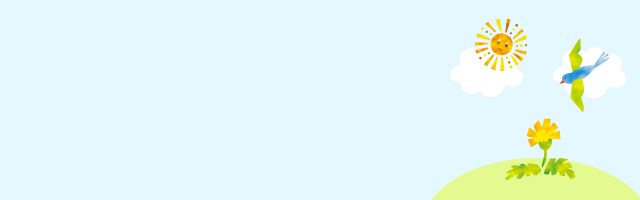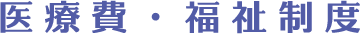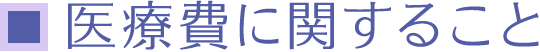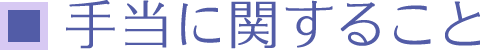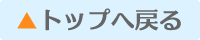小児慢性特定疾病医療給付制度
18歳未満(継続申請は20歳未満まで可能)のお子さんが、対象となる病気で医療を受けたとき、医療費の自己負担分及び入院時の食事代が生計中心者の所得に応じて助成される制度です。また薬代や訪問看護を利用する際の費用も対象となります。制度の概要や対象となる疾病・疾病の状態(現在788疾患)については、次のホームページでご確認ください。
・小児慢性特定疾病情報センター
特定疾患医療(指定難病)給付制度
原因が不明で治療方法が確立していない難病のお子さんで、厚生労働省が定める病気を「特定疾患」といいます。治療が難しく、かつ、その医療費も高額となるため、医療費の負担軽減を目的に実施されています。治療にかかる医療費の一部の助成を受けることができます。制度の概要については次のホームページでご確認ください。
・難病情報センター
自立支援医療制度
心身の障がいの除去や軽減、また安定して医療が受けられることを目的に、病院の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度です。自立支援医療には以下の3種類あります。
- 精神通院医療:精神疾患があり継続した通院が必要とされる方
- 育成医療:身体に障がいがある18歳未満のお子さんで、障がいの除去や軽減のための手術等を受けられる方
- 更生医療:身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、その障がいの除去や軽減のための手術等を受けられる方
※原則1割負担で医療が受けられますが、世帯の所得に応じた自己負担額が設けられています。
身体障害者手帳
身体に障がいのあるお子さんが、さまざまなサービスを利用する場合に必要な手帳です。障がいの程度により1(最重度)~6級(軽度)まで区分されています。
サービスには、日常生活用具の給付や貸与、補装具の交付や修理、ホームヘルプサービス、短期入所施設利用などがありますが、障がいの種類や等級などによって利用できるサービスは異なります。
療育手帳(愛の手帳)
知的障がいのあるお子さんが、さまざまなサービスを利用しやすくするための手帳です。障がいの程度により、A1(最重度)~B2(軽度)まで区分されています。手帳の判定は、児童相談所又は知的障がい者更正相談所で行われますが、市区町村によっては、まず障がい福祉の窓口での相談が必要なこともありますので、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
精神障害者福祉手帳
障がいのあるお子さんが、さまざまなサービスを利用しやすくするための手帳です。てんかん等を含む精神障がいによって、長期にわたり日常生活や社会生活に制約があるお子さんが対象となります。また初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。等級は1~3級まであります。
※いずれの手帳でも取得後に利用できるサービスは、障がいの種類や等級、年齢やお住まいの地域、世帯の所得状況などによって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村障がい福祉の窓口でご確認ください。
小児慢性特定疾患日常生活給付事業
小児慢性特定疾患医療給付制度に該当した方で、身体障がい者手帳等他の制度での日常生活用具の給付が対象とならない方が受けられます。特殊便器、特殊マット、特殊寝台、歩行用支援用具、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器など特定の品目に対して、世帯の所得に応じた自己負担がありますが、購入費用の助成を得ることができます。但し、本制度は市区町村の独自事業であり、行っていない場合もあります。制度の概要については次のホームページでご確認ください。
・小児慢性特定疾病情報センター
横浜市訓練介助器具助成制度
市内在住の障がい児(18歳未満に限られる)であり、身体障がい者手帳等による給付対象とならないお子さんに対し、訓練器具・自助具・介助器具の使用によって訓練や介助効果が期待できると認められた場合、購入経費の3分の2(但し37,800円を限度。眼鏡は26,460円を限度。)が助成される制度です。助成に該当する対象品目があります。
特別児童扶養手当
障がいがある20歳未満のお子さんを養育しているご家族に対し支給されます。該当するおおよその目安は、おおむね身体障がい者手帳1~3級、中~重度の障がいにより介助や安静を必要としていることです。障がい等級は2級まであり、支給額は、1級⇒53,700円、2級⇒35,760円となっています。但し、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。また重症心身障がい児施設等でお子さんが生活されている場合、他公的年金を受けている場合も支給されません。
障がい児福祉手当
日常生活において常時介護が必要とされる状態にある20歳未満のお子さんに対し、精神的、物質的な負担を軽減する一助として手当てが支給されています。月額 15,220円です。但し、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。
神奈川県在宅重度障害者等手当
基準日(毎年8月1日)において、県内に継続して6か月以上居住している在宅の「重度重複障がい者等」に支給されます。「重度重複障がい者等」とは、① 身体、知的、精神障がいのうち、2つ以上重度の障がい者手帳等をお持ちの方、② 特別障がい者手当または障がい児福祉手当を受給されている方です。支給前年度に、施設や病院等に3か月以上継続して入所(入院)していた場合は、対象外となります。また所得による制限があります。支給額は年額60,000円です。
※手当てや医療費助成には、さまざまな制度があります。手続きに必要な書類や窓口は市区町村によって異なります。お住まいの地域の役所にご確認ください。